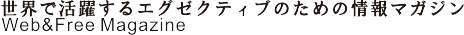人気記事
About&Contact
Events
【開催中〜8/20(水) 東京都・和光】
2025.8.4
グラスの中に“時”を注ぐ──「古酒とアンティークグラスの世界」
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
蒸留酒を味わうことは、単なる飲酒の域を超え、時間そのものを感じる儀式である──。そんな哲学を体感できる特別な催しが、銀座・和光 本店地階アーツアンドカルチャーにて開催中だ。
「古酒とアンティークグラスの世界」は、ウイスキーインポーターの第一人者、松永広人氏監修による希少な古酒とオールドグラスを、アンティークの家具の特別展示による空間演出も併せて展示販売するもの。
会場には、80年の時を経たスコッチを中心とするウイスキーやコニャックが揃い、その歴史を受け止める器として、オールドグラスといわれるラリックやバカラのグラスを用意。
本企画は、2025年7月20日にオープン1周年を迎えた、和光アーツアンドカルチャーの記念イベントのひとつとして行われるもの。「時の舞台」をコンセプトに、洗練された品々を通して本質的な豊かさを提供するサロン空間で、“味わうこと”を超えた“時間と交わる体験”が叶う。
◆古酒とアンティークグラスの世界
【会期】開催中~2025年8月20日(水)
【会場】銀座・和光 本店 地階 アーツアンドカルチャー(東京都中央区銀座)
【営業時間】11:00~19:00
【休業日】会期中無休
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
関連記事
投稿 グラスの中に“時”を注ぐ──「古酒とアンティークグラスの世界」 は Premium Japan に最初に表示されました。
Features
夏休みの思い出に、つくる喜びとサステナブルな学びを
2025.8.3
WHGホテルズ×ガンプラの夏限定プロジェクト『ガンダム R 作戦 with WHG HOTELS』
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
日本が誇るプラモデル文化の象徴「ガンプラ(ガンダムのプラモデル)」が、発売から45周年を迎えたのを記念して、藤田観光株式会社が運営する全国32の「WHGホテルズ」」(ワシントンホテル/<wbr />ホテルグレイスリー/ホテルフジタ/ホテルタビノス)と、株式会社BANDAI SPIRITSがコラボレーション。8月31日(日)まで、『ガンダムR(リサイクル)作戦 with WHG HOTELS』を開催している。
「ガンダムR作戦」とは、回収した「ガンプラ」のランナー(プラスチック枠)をリサイクルし、新たなガンプラ「エコプラ」として生まれ変わらせる、循環型社会の実現を目指すリサイクルプロジェクト。2021年より始動し、全国各地で体験型イベントを展開している。
今回のコラボレーションでは、全国の対象ホテルに宿泊した小学生に、再生素材から生まれた「エコプラ」のガンプラ体験キットを合計10万個プレゼント。工具を使わずに組み立てられるため、初めてプラモデルに触れる子どもでも、安心して“つくる喜び”を味わえるのが魅力だ。さらに、各ホテルには使用済みランナーを回収するリサイクルボックスも設置され、ものづくりを楽しみながら環境への意識を育む工夫も。
※ガンプラコラボルーム イメージ
また、「東京ベイ有明ワシントンホテル」「ホテルグレイスリー⽥町」、「キャナルシティ・福岡ワシントンホテル」では、8月31日(日)までの期間限定で、ガンプラ制作に没頭できるコラボルーム「“MG RX-78-2 GUNDAM Ver.3.0” ROOM」がオープン。客室には専用工具がずらりと並ぶほか、コックピット型のデスクやガンプラのモデル展⽰など、ファンの⼼をくすぐる空間と楽しい仕掛けも。
世代を超えて愛されるガンダムの世界に、サステナブルな視点を添えた夏限定の宿泊体験。自由研究や親子の思い出づくりにもおすすめだ。
◆『ガンダムR作戦 with WHG HOTELS』
【宿泊期間】開催中~2025年8月31日(日)チェックアウトまで
【対象者】全国の対象施設に宿泊した小学生 ※上限数に達し次第終了
【提供商品】エコプラ 1/144 RX-78-2 ガンダム 組み立て体験会ver.(⾼さ 12.5cm) ※ 1滞在につき 1
【対象施設】全国の WHGホテルズ 32 施設
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
関連記事
投稿 WHGホテルズ×ガンプラの夏限定プロジェクト『ガンダム R 作戦 with WHG HOTELS』 は Premium Japan に最初に表示されました。
Lounge
Premium Salon
京都通信
2025.7.28
京都の寺社は朝が美しい──静けさと涼を求めて早朝さんぽ&京のゆば粥御膳で朝食を
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
夏の盛りを迎えた京都。
どこへ出かけても、厳しい暑さと人波に気後れしてしまう……。そんな季節だからこそ、おすすめしたいのが、静けさに包まれた朝のひとときです。
東寺や下鴨神社、北野天満宮など、早朝から参拝できる寺社を訪ねたあとは、二条城で美しい庭園を眺めながら朝食をいただく特別なひとときを。
喧噪を離れ、凛とした空気に身をゆだねる、京都ならではの朝の過ごし方をご紹介します。
東寺 5:00開門
京都で最も早く開門する、朝の聖域
五重塔がシンボルの世界遺産・東寺は、京都の寺院のなかでもとくに朝が早く、開門はなんと5時。まだ街が目覚めきらない時間帯、澄んだ空気と静寂に包まれた境内を歩くと、心がすっとほどけていくような感覚に満たされます。
朝焼けの空にそびえる国宝「五重塔」。日の出時刻の前後数十分がとくに美しい。
朝6時からは、弘法大師・空海が住居としていた御影堂(みえどう)で「生身供(しょうじんく)」と呼ばれる法要が行われています。誰でも参加できるので、希望する方は5時50分頃までに御影堂の唐門または西門前へ。
この法要では、国宝である本尊・弘法大師像が開帳され、一の膳、二の膳、お茶が供えられます。読経の声が静かに響く堂内で参拝者も一緒に手を合わせ、最後には空海が唐から持ち帰ったという仏舎利(お釈迦様の遺骨)を授けてもらうことができます。
境内の北西に位置する「御影堂」。南北朝時代の建物で、国宝に指定されている。
さらに、毎月21日には境内で「弘法市」が開かれ、早朝から骨董品や古着、食べ歩きできるフード類など、多彩な露店がずらりと並びます。第1日曜日には骨董市「東寺ガラクタ市」も開催されているので、掘り出しものを見つけに訪れてみては?
東寺(とうじ)
住所 京都市南区九条町1
TEL 075-691-3325
開門時間 5:00〜17:00
HP https://toji.or.jp/
Instagram @toji_official
下鴨神社 6:30開門
太古の森を歩く、清めの朝
京都最古の神社のひとつである下鴨神社は、朝6時半から参拝可能。境内を歩けば、木々の葉をわたる風の音や、小鳥のさえずりが、心にそっと寄り添ってくれるよう。早朝は訪れる人もまばらで、清々しい空気に包まれています。
鮮やかな朱塗りの「楼門」は重要文化財に指定されている。
境内の大半を占める「糺の森」に広がるのは、縄文時代から続く原生林。うっそうと茂る木々のあいだを歩けば、森そのものが神域であることを実感。朝露の匂いをふくんだ森の空気に、心がすっと癒やされていくのを感じます。
この森を含む下鴨神社は、世界文化遺産にも登録されており、自然遺産としても貴重な存在です。手つかずの植生が今なお守られていることに、自然と敬意の念が湧いてきます。
太古の自然を遺す「糺の森」は広さ3万6千坪。原生林の間を静かに小川が流れている。
境内には、美麗の神様を祀る河合神社や、縁結びで知られる相生社などの摂社・末社も点在。静かな時間の流れに身をまかせ、それぞれの社をゆっくりめぐってみるのもおすすめですよ。
北野天満宮 7:00開門
朝の光に映える御社殿の壮麗な佇まい
学問・厄除・芸能の神様として知られる菅原道真公を祀る北野天満宮。こちらは朝7時から参拝が可能です。
後西天皇(1637-1685)宸筆の勅額『天満宮』が掲げられた「三光門」。
ゆるやかに境内を進んでいくと、やがて見えてくるのが「三光門」。壮麗な造りがひときわ目を引く、シンボル的な建築です。
その奥に佇む御本殿は、国宝に指定されており、桃山時代の建築美を今に伝える貴重な存在。唐破風や黄金色に輝く装飾、精緻な彫刻など、細部に宿る技を、朝の光のなかでゆっくりと味わうことができます。
また、天満宮といえば菅原道真公がこよなく愛した「梅」も有名。御神木として大切に受け継がれる梅のほか、境内の随所に梅の神紋が見られます。
“天神さんの日”として親しまれる縁日。境内には食べ物の屋台も多く、お祭り気分が楽しめる。
毎月25日には縁日「天神市」が開催され、朝6時ごろから骨董や古書、食器、和雑貨など、多彩な露店が並びます。ふと足を止めた先で、思いがけない品との出合いがあるかもしれません。
北野天満宮(きたのてんまんぐう)
住所 京都市上京区馬喰町
TEL 075-461-0005
開門時間 7:00〜17:00 ※毎月25日は6:30開門
HP https://kitanotenmangu.or.jp/
Instagram @kitano_tenmangu
二条城・香雲亭 9:15~10:15
歴史に抱かれる庭園で、ゆば粥朝御膳を
寺社をめぐって静かな朝の時間を味わったあとは、二条城へ。世界遺産にも登録されているこの城のなかに、通常は非公開の「香雲亭」があります。夏の朝のひととき、特別にその扉が開かれ、美しい庭園を眺めながら朝食をいただける貴重な体験が待っています。
江戸時代の豪商・角倉(すみのくら)家の屋敷跡から移築された「香雲亭」。
提供されるのは、祇園・円山公園に本店を構える「京料理いそべ」の料理。自家製の汲み上げゆばを使ったやさしい味わいの「ゆば粥」と季節の小鉢を添えた「京のゆば粥御膳」です。
今年は大阪・関西万博の開催を記念し、月替わりの逸品には地元・京都の食材を中心に関西各地の恵みが盛り込まれています。7月の「鱧おとし(大阪府/兵庫県)」から始まり、8月は「賀茂茄子のしぎ焼き(京都府)」、9月は「鮎の竜田揚げ(滋賀県/和歌山県)」を予定。見た目にも涼やかな品々が、朝の身体にやさしく染みわたります。
8月の「京のゆば粥御膳」。献立には、賀茂茄子のしぎ焼きやゆば粥がラインナップされる。
香雲亭の目の前に広がるのは、和洋折衷のユニークな造りが特徴の庭園「清流園」。東半分は芝生を敷き詰めた洋風ですが、香雲亭のある西半分は池を中心に四季折々の美しさを見せる和風庭園。朝の光をやわらかく照らす水面と、全国から集められた銘石が織りなす変化に富んだ景色とともに、料理を味わう朝──そんな贅沢がここにあります。
朝食の提供は2025年7月15日(火)から9月30日(火)まで。完全予約制・各日40名限定なので、早めの予約がおすすめです。
特別朝食「京のゆば粥御膳」(とくべつちょうしょく「きょうのゆばがゆごぜん」)
開催場所 二条城内 清流園・香雲亭
開催日時 2025年7月15日(火)~2025年9月30日(火) 9:15~10:15
料金 4,200円(税込) ※入城料が別途必要
申し込み 参加希望日の前日15:00までに要予約
予約連絡先 075-551-1203(京料理いそべ/受付時間10:00〜15:00)
元離宮二条城(もとりきゅうにじょうじょう)
住所 京都市中京区二条通堀川西入二条城町541
TEL 075-841-0096
入城時間 8:45〜16:00(17:00閉城)
入場料 一般800円、中高生400円、小学生300円
HP https://nijo-jocastle.city.kyoto.lg.jp/
Instagram @nijojocastle
涼やかな空気に包まれる、京都の朝。静けさの中で心をととのえ、癒やされるひとときを過ごしてみませんか。
Text by Erina Nomura
野村枝里奈
京都在住のライター。大学卒業後、出版・広告・WEBなど多彩な媒体に携わる制作会社に勤務。2020年に独立し、現在はフリーランスとして活動している。とくに興味のある分野は、ものづくり、伝統文化、暮らし、旅など。Premium Japan 京都特派員ライターとして、編集部ブログ内「京都通信」で、京都の“今”を発信する。
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
Lounge
Premium Salon
京都通信
Premium Salon
関連記事
投稿 京都の寺社は朝が美しい──静けさと涼を求めて早朝さんぽ&京のゆば粥御膳で朝食を は Premium Japan に最初に表示されました。
Features
【開催中〜10/26(日) 新潟県・新潟県立万代島美術館】
2025.8.1
「さくらももこ展」@新潟県立万代島美術館
©さくらももこ ©さくらプロダクション
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
まんが家にとどまらず、エッセイスト、作詞家、脚本家としても独自の世界観を築いた稀代のアーティスト、さくらももこ。その創作の軌跡をたどる展覧会が、10月26日(日)まで新潟県立万代島美術館にて開催されている。
『ちびまる子ちゃん』その58 まる子 偏食をする の巻 扉絵(後期のみ)
©さくらプロダクション
『もものかんづめ』奇跡の水虫治療 (通期)
©さくらプロダクション
『COJI-COJI』第1話 コジコジはコジコジの巻 (通期)
©さくらももこ
1992年 (後期のみ)
©さくらプロダクション
誰もが一度は目にしたことのある国民的まんが『ちびまる子ちゃん』や、290万部を超える大ベストセラーとなったエッセイ『もものかんづめ』、哲学的な余韻を残す『コジコジ』など多彩な作品を、直筆原稿やカラー原画とともに紹介。
また、「アトリエより」と題した終章では、愛用品や、ひとつひとつ丁寧に描かれた小さなイラストを展示。仕事でもプライベートでも、みんなを楽しませたり、面白がらせることが大好きだったという彼女の素顔にも出会える。
『ももこのファンタジック・ワールド コジコジ』夏の ようせいの おくりもの の巻 (前期のみ)
©さくらももこ ©さくらプロダクション
『ももこのまんねん日記』 (後期のみ)
©さくらももこ
「描く」と「書く」を自在に行き来しながら、ユーモアと愛あふれる眼差しで日常を見つめ続けたさくらももこ。今なお色褪せることのないその魅力に、あらためて触れてみてはいかがだろうか。
◆「さくらももこ展」
【会期】開催中~2025年10月26日(日)
前期:7月12日(土)~8月31日(日)、後期:9月2日(火)~10月26日(日)
※会期中、一部展示替えあり
【会場】新潟県立万代島美術館(新潟県新潟市中央区万代島5-1 朱鷺メッセ内 万代島ビル5F )
【時間】10:00~18:00(観覧券の販売は17:30まで)
【休館日】7月28日(月)、8月4日(月)、18日(月)、9月1日(月)、8日(月)、29日(月)、10月6日(月)、20日(月)
【観覧料】一般 1,500円、大高生 1,200円、中学生以下無料
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
関連記事
投稿 「さくらももこ展」@新潟県立万代島美術館 は Premium Japan に最初に表示されました。
Lounge
Premium Salon
編集部&PJフレンズのブログ
2025.7.30
「界 奥飛騨」で過ごす夏の温泉旅。さわやかな風と湯けむりに包まれて
「飛騨MOKU(もく)の間」、施設全体に天然木と飛騨の匠が生き、各エリア匠の作品がちりばめられ、まるでショールーム。内湯温泉は、滞在中24時間好きなときに!
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
2024年9月に開業したばかりの「界 奥飛騨」への旅に誘われ、参加してきました。バスタ新宿から高速バスに乗り込み、一路奥飛騨温泉郷へと向かいます。バスの乗車時間は5時間ほど。読書をしたり、うとうとしたりしている間に景色はどんどんと変わり、旅への期待が高まっていきます。
奥飛騨温泉郷とは、飛騨山脈(北アルプス)の麓に点在する平湯、福地、新平湯、栃尾、新穂高の5つの温泉地の総称です。「界 奥飛騨」は、その中でも最古の歴史を持つ平湯温泉にあります。平湯温泉は、日本三大湧出量を誇る名湯として知られている温泉です。
「界 奥飛騨」に到着したら、早速足湯を体験しました。北アルプスの雄大な眺めも素晴らしく、そして何といっても涼しい!ここ「界 奥飛騨」は標高1250mに位置するとのことで、東京の暑さと比べたら天国のよう。長旅の疲れも一瞬にして吹き飛びます。
独自の「湯治文化」を体現した足湯の楽しみ方すぐ楽しめます
館内は、「界」の特長でもある、地域の文化に触れることができます。さまざまな内装、家具、小物のかざり、モダンなデザインと木の温もりを感じるしつらえです。
今回宿泊したのは「飛騨MOKU(もく)の間」。地元の伝統的な漆塗りである飛騨春慶 (ひだしゅんけい)はウォールアートや客室サインに、飛騨染のオリジナルクッション まで。曲木(まげき)をモチーフにしたヘッドボードには、空間が軟かく感じるから不思議です。
客室の露天風呂ももちろん温泉です!バスタブの横には寝転がれるほどの大きさのソファーもあり、何度もお湯につかり、ゆったりのんびり過ごすことができました。
地域の文化が室内装飾に。
温泉から濡れたまま上がれるソファ。
細部までこだわりぬいたルームキー。
せっかくなので大きなお風呂に入りたいもの。露天風呂を備える、温泉棟(湯小屋棟)にも行ってみました。内湯には、源泉掛け流しの「あつ湯」とリラックス効果の高い「ぬる湯」という2種類の湯船があり、湯治気分を高めてくれます。
露天風呂は、北アルプスの「雪の回廊」をイメージした白い壁で囲まれており、真上には巨大な穴がぽっかりと開いているのがとてもユニーク。日中は青空を、夜には星空を眺めながら湯舟で手足を伸ばして入ることができました。
雪の回廊をイメージした、まるみのある曲線的なデザイン。
旅の楽しみには、食事も欠かせません。半個室でプライベート感のある食事処で時間をかけて「飛騨牛の味噌すき会席」をいただきました。味噌仕立てのすき焼きは初めての経験です。卵ではなく、長芋のすりおろしを飛騨牛に絡めるというアイデアが面白い。驚きの一品でした。
上質な飛騨牛の味噌仕立てのすき焼きは、タマゴでなく長芋に絡めていただき、なんとも新鮮な味わい。
朝はいつもより早く起床して、中庭で開催される「現代湯治体操」に参加しました。日常のあわただしさから逃れて、身体をゆっくりと目覚めさせ、すっきりした気分になります。そして、朝食へと向かいます。
夕食であんなにたくさん食べたのに、色とりどりの朝食に箸が進みます。飛騨近辺の野菜などがふんだんに使われた、ヘルシーな朝ごはんです。
体にやさしい目覚めの体操に参加後の朝食。品数が多く、保存食の干し野菜をふんだんに使ったお味噌汁は、ぜひ自宅でも取り入れたい野菜メニュー。
「界」を訪れたなら、地域の文化体験「ご当地楽」にはぜひトライしてください。「界 奥飛騨」では、「飛騨の匠体験」風呂敷用曲木のハンドル制作を体験することができます。お湯に一晩漬けて柔らかくなった木を曲げる感触がなんとも楽しいですし、お土産として持ち帰ることができます。いろいろな風呂敷を購入したくなりました。
飛騨の森を感じられるデザイン壁など、体験ルームの装飾も素敵なんです。さまざまなノミやカンナなどの工具の展示の様子がなんともかわいい。
周辺を観光するなら、おくひだマウンテンバス※がお勧めです。景色の良さを満喫できる路線バスも充実し、マイカー・タクシーなどでも「平湯バスターミナル」から「新穂高ロープウェイ」のルートでこの景色が楽しめるのです。20㎞にわたる5つの奥飛騨温泉郷をバスで走り抜け、「新穂高ロープウェイ」では、空中の高原散歩気分を味わえます。さまざまな表情を見せる美しい北アルプスの山々が堪能できるそうなので、ぜひ期間中に訪れたいものです。
※おくひだマウンテンバスは2025年7月18日で特別運行終了しています。
おくひだマウンテンバスはルーフトップからの眺めが圧巻。風を感じながら奥飛騨を走り抜けます。
写真提供:おくひだマウンテンバス
日本初の二階建てロープウエイで、頂上に重装備なく行け、新しくおしゃれに整備された頂上から360度の北アルプスを3000m級の山々を2000mの高さから楽しめます。
写真提供:奥飛騨観光
北アルプスの眺めの壮大さ、奥飛騨の自然と文化に満たされた旅になりました。そして今度来るときは、二泊はマスト。お湯も、自然も満喫する旅にしたいと願いながら、帰途に就きました。
川瀬マリ子 Mariko Kawase
プレミアム ジャパン マーケティングスタッフ
愛犬と国内旅行へ行くことを楽しんでいます。
関連リンク
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
Lounge
Premium Salon
編集部&PJフレンズのブログ
Experiences
Premium Calendar
永遠の聖地、伊勢神宮を巡る
2025.7.28
伊勢神宮で古くから行われる「お祓い」の儀式と「御塩」の意味
神宮で行われる大祓(おおはらい)の様子。榊の枝に麻苧(あさお)を付けた大麻(おおぬさ)と呼ばれる祓い具で、神職たちを祓い清める。すべてが清らかな姿に、見ていた子どもが思わず「きれい」と声を上げた。
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
何度訪れても、いつ参拝しても、伊勢の神宮は清々しい。
そう思う理由の1つに、伊勢神宮の内宮に流れる五十鈴川の存在がある。清らかな流れと心洗われる瀬音、そして、内宮の御手洗場(みたらし)で手を清めるときの、ひんやりとした水の感触。五感を伴って刻まれたその清々しさの記憶は、神宮という言葉とともに鮮やかに蘇ってくる。
五十鈴川の清らかな流れ。
伊勢神宮の大祓(おおはらい)とは
神宮の大祓は、毎年6月、12月の晦日(みそか=月の最後の日)と、大祭が行われる前の月、たとえば、2月の祈年祭のための大祓は、前の月である1月の晦日、というように、4月、5月、9月、10月、11月の晦日の、計8回行われている。大祭に先立ち、大宮司以下の神職や楽師たちが、内宮の第一鳥居近くの、注連縄が張られた「祓所(はらえど)」と呼ばれる場所で、それぞれの罪や穢れを祓い清めるのだ。
神道でいう罪や穢れは、日常生活の中で知らず知らずのうちに身に付いてしまったさまざまなものを指す。一説では、罪は「包む身(<u>つ</u>つむ<u>み</u>)、穢れは「気枯(けが)れ」を指し、人間本来の姿を包んで隠してしまうことが罪であり、「気」を枯らす、つまり、生命力を減退させてしまうのが穢れだと言われている。つまり、人間はもともとすばらしい体を持ちながら、それを覆い隠すようなものが付着するために本来の姿が隠れてしまい、病気や災難に遭うなどの好ましくない状態になってしまう、というのだ。
内宮の五十鈴川の川辺で行われる大祓を終え、斎館に戻る神職たち。
禊は水で身を清めること、
祓いは水や火、塩、さらに祓い具などによって罪や穢れを除き去ること
そんな罪や穢れを除き去るため、日本では古来、禊(みそぎ)や祓いが行われてきた。
禊とは、水を使って身を清めること。特に海や川などの清らかな水は、穢れを浄化する神聖な力があるとされ、古くは神前に流れている川で身を清めたという。内宮の御手洗場も、本来は神宮の祭祀に関わる人々が禊をする場所だった。現在お参りの前に手水舎で手を洗い、口をすすぐのも、簡略化された禊を行っていると考えられている。
一方祓いは、水や火、塩、さらに祓い具などによって罪や穢れを除き去ること。神社で正式参拝をしたことがある人なら、神事に先立ち、神職が祓いの詞(ことば)である祓詞(はらえことば=)を奏上した後で、大麻(おおぬさ)、つまり、榊の枝や素木(しらき)の棒に、白い紙を特殊な断ち方をして折った紙垂(しで)や、麻の繊維を原料とした麻苧(あさお)と呼ばれる糸を付けた祓い具で、参列者の頭上を左右左と振る、修祓(しゅばつ)の儀式に立ち会ったことがあるだろう。
手水舎は、簡略とはいえ、心静かに身を清める禊の場所。内宮の別宮、瀧原宮で。
たとえ意味は知らなくても、神社でお参りすることは、参拝者それぞれが、古来重視されてきた禊や祓いを簡略ながらも行って、心身を清浄にし、その上で神前に進み出るという行為をしているわけだ。
ケからハレへ
神社をお参りしようという思い自体が浄化作用に繋がっている
「祝詞では、よく『今日の生日(いくひ)の足る日』、つまり、『今日は生き生きとした満ち足りた日である』という文言が使われます。神社にお参りに来るのは、まさにそんな日で、日常であるケの状態からハレになるということです。つまり、神社にお参りをするという発想を思いつくこと自体が、自分をケからハレに変えることであり、その人の中で浄化作用である祓いを行っていると、私は思います」
神宮の広報室次長の音羽悟さんは言う。
興味深いのは、罪や穢れが道徳的、人為的なものだけではないということだ。
「たとえば落雷や大雨に遭うなど、自然界で発生するいろいろな災異を受けてしまうことも、自分の常日頃の行いに罪や穢れがあるからだと、古代人は考えていたのです」と音羽さん。
古代においての罪や穢れは、個人の問題だけでなく、共同社会の幸福発展にとっても障害となると考えられていたようだ。
大祓の儀式も、もとは国家の神事として行われるものだった。8世紀に制定された『神祇令(じんぎりょう=国家祭祀の根本的な事柄をまとめたもの)』によれば、毎年6月と12月に、恒例の神事として大祓を行うことが定められていたという。
大祓では、まず神職それぞれに榊の枝が手渡される。
権禰宜が大麻の前で、細かく切った白い紙(切麻=きりぬさとも呼ばれる)と米粒を左右左と散ずる「銭切(せんぎり)」、「散米(さんまい)」の所作を行った後、大祓詞を微音で唱える。その間、神職たちは榊を手に平伏。
「古代人はサイクルをとても大事にしていました。繰り返すという循環の中で、節目節目に祓いを行って原点に立ち返る。つまり、本来祓いとは、人間が社会生活を営む上で、必要最低限守らなければならない規範であり、原点回帰でもあって、ものごとが秩序正しく循環していくために規則正しく行っていく、そこに意義があると私は考えています」
加えて、災害や天変地異など、もろもろの忌まわしいことが起こったときも、臨時で大祓が行われることがあったという。それによって、国土上の一切の罪や穢れが祓われて、災いを除け、吉祥を招くことができると信じられていたのである。
祓い具で祓い清められた後、神職たちは低頭して小さく2度、柏手を打ち、榊に息を吹きかける。
神話から紐解く、祓いが吉祥を招く理由
だが、ここで疑問も起こる。なぜ祓いをすることで、吉祥を招くことができるのか。
その答えを導くヒントは、神話の中に記されている。
『古事記』によれば、イザナギノミコトが、亡き妻のイザナミノミコトに会いたくなって黄泉(よみ)の国を訪れた際、穢れに触れ、それを祓うために、身にまとっていた衣類や所持品を投げ捨てて海水に浸かったとされ、これが禊のはじまりと言われている。だが、神話はそこで終わらない。イザナギノミコトは、それを機に次々と神々を生み、最後に天照大御神と月讀命(つきよみのみこと)、須佐之男命(すさのおのみこと)の3貴神を生んだ。つまり、最も貴いとされる3柱の神々は、イザナギノミコトが罪や穢れを除き去った後に生まれたのである。
では、国家の神事である大祓とは、どのようなものだったのだろう。
奈良時代に朝廷で行われていた6月と12月の恒例の大祓では、平城京の正門である朱雀門の前に官吏などの男女が集まり、まず大祓詞(おおはらえのことば)が読み上げられた後、祓いを受けたとされている。さらに、各々が自身の身代わりとなる形代(かたしろ)の木製の人形(ひとかた)を撫で、もしくは息を吹きかけて、罪や穢れを人形に付着させ、川や溝に流したという。
現在6月の晦日に、各地の神社で行われる「夏越(なごし)の祓え」は、そんな大祓の儀式が民間に定着した行事。広く「茅の輪くぐり」で知られているものの、神社によっては、氏子が人形で体を撫で、神社に納める風習が今も根強く残っている。人間が知らず知らずのうちに身に付けた罪や穢れを除き去るという禊や祓いの風習は、さまざまな形で一般にも広く浸透し、今に受け継がれているのだ。
榊が用いられる神宮の大祓と大祓詞の謎
一方、神宮で行われる大祓では、人形ではなく、榊の枝が用いられる。
大祓が始まるのは、午後3時(1月、4月、10月、11月、12月)、もしくは4時(5月、6月、9月)。五十鈴川の瀬音が聞こえる祓所で、まず榊を手渡された神職や楽師たちは、権禰宜が大祓詞を微音で唱える間、榊を手に平伏(へいふく)。終わると、大麻による祓いを受け、各々手にした榊に息を吹きかける。その榊は、儀式が終わった後で五十鈴川に流されるのだ。
ちなみに、大祓詞とは、平安時代中期に編纂された『延喜式』に記載されている、28篇の祝詞の1つ。千数百年以上も前から唱えられてきた、日本最古の祝詞と言われている。なかでも注目したいのは、その後半部分。人々が知らず知らずのうちに犯した罪事(つみごと)は、祓戸(はらえど)4神と呼ばれる4柱の神々のはたらきにより、山から川へと流れ落ち、さらに大海原へ持ち出されて潮の流れに乗り、海底に進んだ後、最後は根の国底の国で消滅するという内容になっている。
神宮の大祓の儀式が川辺で行われるのも、それぞれの罪や穢れを移した榊を川に流すのも、すべて大祓詞に則ってのことなのだ。
「大祓詞には意味がわからない部分が多々あります。たとえば、冒頭部分に登場するカムロギノミコトとカムロミノミコトとは、どんな神様なのか。『古事記』や『日本書紀』には記載がなく、大祓詞にしか登場しないため、具体的なことがわかりません。もっとも、大祓詞は呪言(じゅごん=呪的な目的を果たすために唱える言葉)であり、唱えるということが、何より大事なのだと思います」
祓いに塩が用いられるのは、
罪や穢れを消滅させる海のエキスが詰まっているから?
思えば、修祓などの祓いで、塩や塩湯(えんとう=塩を溶かした湯)が用いられるのも、大祓詞によるのだろう。日本の塩は、海水を採取して作られている。つまり、罪や穢れを消滅させる海のエキスが詰まっている、とも言えるのだ。
神宮では、神事に用いられる塩を御塩(みしお)と呼び、内宮鎮座当時から、二見浦(ふたみがうら)の御塩がお供えされたと伝えられている。現在は、五十鈴川の川水と伊勢湾の海水が混じる、汐合(しおあい)と呼ばれる地に設けられた御塩浜で、日本の伝統的な製塩法である入浜(いりはま)式塩田法を用いて製塩されている。
さまざまな工程を経て、最終的に、三角錐の形に焼き固められた堅塩(かたしお)は、祓い清めに用いる際は砕いて粉状にし、神饌としてお供えするときは、砕いた塊を用いるという。
神宮では入浜式塩田と呼ばれる伝統的な製法で御塩作りが行われている。まず潮の満ち引きを利用して海水を塩田に入れ、砂に塩分を付着させて天日で乾燥。砂をかき起こして鹹水(かんすい=濃度の濃い塩水)を採取する。
採取した鹹水を煮詰めて塩を精製。
「神事で塩が用いられるのは、海そのものがすべての原点になっていることも大きいと思います。『古事記』でも、イザナギノミコトとイザナミノミコトが、天の浮き橋から海に矛を下ろし、海水を『こおろ、こおろ』と掻き鳴らして矛を引き上げると、その先から海水がしたたり落ち、塩が固まって島ができたと記されています。つまり古代人は、海からすべてが生まれるという考え方を持っていたと、私は思うのです」
御塩はさまざまな場面で用いられる。おまつりに先立ち、修祓で神饌や神職を祓い清めるのはもちろん、月次祭の由貴夕大御饌(ゆきのゆうおおみけ)の翌日、勅使が天皇陛下の幣帛(へいはく)を奉る奉幣の儀でも、内宮の第二鳥居で、幣帛が納められた辛櫃(からひつ)の御塩での祓い清めが行われる。
たしかに塩や塩湯でお清めされるのは、大麻による祓いを受け、罪や穢れを除き去った後のことである。『古事記』の中で、イザナギノミコトが禊や祓いを行った後で3貴神を生んだように、人も祓いを受けて原点に立ち返ることで、何か新たなものを生むことができるのかもしれない。
長い歴史を持つ禊や祓いの世界。知れば知るほど奥が深い。
Text by Misa Horiuchi
伊勢神宮
皇大神宮(内宮)
三重県伊勢市宇治館町1
豊受大神宮(外宮)
三重県伊勢市豊川町279
文・堀内みさ
文筆家
クラシック音楽の取材でヨーロッパに行った際、日本についていろいろ質問され、<wbr />ほとんど答えられなかった体験が発端となり、日本の音楽、文化、祈りの姿などの取材を開始。<wbr />今年で16年目に突入。著書に『おとなの奈良 心を澄ます旅』『おとなの奈良 絶景を旅する』(ともに淡交社)『カムイの世界』(新潮社)など。
写真・堀内昭彦
写真家
現在、神宮を中心に日本の祈りをテーマに撮影。写真集「アイヌの祈り」(求龍堂)「ブラームス音楽の森へ」(世界文化社)等がある。バッハとエバンス、そして聖なる山をこよなく愛する写真家でもある。
関連リンク
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
Experiences
Premium Calendar
永遠の聖地、伊勢神宮を巡る
Premium Calendar
関連記事
投稿 伊勢神宮で古くから行われる「お祓い」の儀式と「御塩」の意味 は Premium Japan に最初に表示されました。
Events
【8/30(土)~11/3(月・祝) 東京都・泉屋博古館東京】
2025.7.29
特別展 巨匠ハインツ・ヴェルナーの描いた物語 ―現代マイセンの磁器芸術
《サマーナイト》ティーサービス マイセン 1974年頃~ 個人蔵 装飾:ハインツ・ヴェルナー 器形:ルードヴィッヒ・ツェプナー
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
泉屋博古館東京にて、現代マイセンを代表するアーティスト、ハインツ・ヴェルナーの創作世界に迫る特別展「巨匠ハインツ・ヴェルナーの描いた物語 ―現代マイセンの磁器芸術」が、2025年8月30日(土)より開催される。
《梅樹竹虎図大皿》 マイセン 18世紀 愛知県陶磁美術館蔵
ヨーロッパで初めて硬質磁器の焼成に成功した、ドイツの名窯マイセン。歴史ある名陶に現代的な息吹を吹き込んだのが、ハインツ・ヴェルナーだ。
《アラビアンナイト》コーヒーサービス マイセン 1967年頃~ 個人蔵 装飾:ハインツ・ヴェルナー 器形:ルードヴィッヒ・ツェプナー
彼は、「アラビアンナイト」「サマーナイト」「ブルーオーキッド」など、現代マイセンを代表する作品のデザインを手がけ、世界中の愛好家を魅了してきた。
《ほら吹き男爵(ミュンヒハウゼン)》コーヒーサービス マイセン 1964年頃~ 個人蔵 装飾:ハインツ・ヴェルナー 器形:エアハルト・グローサー、アレクサンダー・シュトルク、ルードヴィッヒ・ツェプナーの共作
会場では、ヴェルナーが手がけたティー&コーヒーサービス、陶板画(プラーク)など、初期から晩年に至る代表作を一堂に展示。磁器という限られた空間に、色彩と想像力と思想を凝縮させた作品には、東洋の陶磁文化からの影響や、神話・文学への深い造詣、そして色彩と線が織りなす詩的な構成力が感じられる。
ティターニアとツェットル 《サマーナイト》ティーサービスより マイセン 1974年頃~ 個人蔵 装飾:ハインツ・ヴェルナー 彫像:ペーター・シュトラング
磁器芸術に新たな息吹を吹き込んだ巨匠ハインツ・ヴェルナー。その軌跡と魅力を、この機会に体感してはいかがだろうか。
◆特別展 巨匠ハインツ・ヴェルナーの描いた物語 ―現代マイセンの磁器芸術
【会期】 2025年8月30日(土)~11月3日(月・祝)
【会場】泉屋博古館東京(東京都港区六本木1-5-1)
【開館時間】11:00~18:00(金曜は19:00まで)
※入館は閉館30分前まで
【休館日】月曜および9月16日(火)、10月14日(火)
※9月15日(月・祝)、10月13日(月・祝)、11月3日(月・祝)は開館
【観覧料】一般 1,500円、学生 800円
※18歳以下無料
関連リンク
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
関連記事
投稿 特別展 巨匠ハインツ・ヴェルナーの描いた物語 ―現代マイセンの磁器芸術 は Premium Japan に最初に表示されました。
Events
9月18日(木)開催「ホテルオークラ京都の日帰り旅行企画」
2025.7.28
京都で山科言親氏が語る「宮廷文化の伝統と、その継承 第1回衣紋~宮廷装束~」
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
第1回は「衣紋 ~宮廷装束~」として、装束の着付けの技術「衣紋」を、11月開催予定の第2回は「薫香」へと続く。
第1回では、開山以来多くの皇女が住持を務めた尼門跡寺院、「百々御所」とも呼ばれる、京都市上京区の「宝鏡寺」を特別拝観する。その後は場所を移して、京都西陣で創業より 300 余年の歴史ある名店「萬亀楼」にて約20種類の料理を盛り込んだ竹籠弁当をいただく。<wbr />御所ゆかりの生間流式庖丁・有職料理を正式に継承する老舗の、<wbr />雅やかな技法や礼儀作法でのおもてなしに触れる機会になる。
お食事の後は、2 階広間において、山科氏による衣紋の解説とともに着装を見学し、千年の長きにわたる京都の宮中文化、まち、人々の暮らしについてのお話を伺う。
衣紋道とは十二単や束帯などの華麗な装束を着付けるための技術を体系化したものである。平安時代末期に朝廷内の装束が柔装束から強装束へと変化したことにより、一人で着ることが困難となったため、仕立てや着付けに長けた衣紋者が必要とされるようになった。山科家は代々宮中の衣装である装束の調進・着装を家職とし、30代家元後嗣の衣紋道山科流若宗家の山科言親氏に受け継がれている。
日本の伝統文化や歴史に触れ、普段は見聞きする機会のない宮廷の日常を垣間見れる体験は非常に貴重な機会となるはずだ。
山科 言親 (やましな ときちか)氏
衣紋道山科流若宗家。1995年京都市生まれ、京都大学大学院人間・環境学研究科修士課程修了。代々宮中の衣装である“装束”の調進・着装を伝承している山科家(旧公家)の30代後嗣。三勅祭「春日祭」「賀茂祭」「石清水祭」や『令和の御大礼』にて衣紋を務める。各種メディアへの出演や、企業や行政・文化団体への講演、展覧会企画や歴史番組の風俗考証等も行う。山科有職研究所代表理事、同志社大学宮廷文化研究センター研究員などを務め、御所文化の伝承普及活動に広く携わる。
◆季節の旅 特別プラン「宮廷文化の伝統と、その継承 第 1 回 衣紋 ~宮廷装束~」
【日程】 2025 年 9 月 18 日(木)
【料金】 1 名様 67,000 円
※食事、移動費、諸税、その他行程に必要な費用を含みます。
【予約・お問い合わせ】
ホテルオークラ京都 季節の旅事務局
TEL:075₋211-5111(代表)
※申し込み期限 2025 年 9 月 8 日(月)(満席・催行中止の場合はこの限りではありません)
関連リンク
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
関連記事
投稿 京都で山科言親氏が語る「宮廷文化の伝統と、その継承 第1回衣紋~宮廷装束~」 は Premium Japan に最初に表示されました。
いよいよ夏本番。気温がより高まるこれからの時期に気になるのが「車内の温度上昇」です。炎天下の車内に置いてはいけないものについて、All About 中古車ガイドの籠島康弘さんにお聞きしました。※画像:PIXTA
Lounge
Premium Salon
これを食べなきゃ人生ソンだよ
2025.7.25
東京の海南鶏飯 シンガポールチキンライス ベスト5~真夏じゃなくても一年中食べたい!
15年間、大使館御用達を務めているという「シンガポール海南鶏飯」の”シンガポールチキンライス”。
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
さあ、海南鶏飯(カイナンケイハン)、つまりシンガポール・チキンライスの出番だぜ!
っていうようなコーフンは、皆さんにはないですかね。今回は、「海南鶏飯食堂 麻布十番店」、「シンガポール海南鶏飯 水道橋店」、「新東記 CLARK QUAY 大手町」、「海南チキンライス 夢飯」、「威南記海南鶏飯 (ウィーナムキー ハイナンチキンライス) 」など、東京のベスト5を選んでみた。
やはり、暑い季節には、暑い国からの料理ですな。とはいえ、最近の日本はシンガポールよりも暑いけどね(笑)。
筆者は、ランチは毎日これでもいいっていうくらい好きなんですな。その証拠に、先月、シンガポールに5泊したんだが、アホかと思われるほど、毎日違う店でこれを食べた。郊外の安い店で400円、有名店で1200円ぐらいの幅があった。
はい、というワケで、2000年にシンガポールから東京に初上陸した海南鶏飯は、四半世紀が過ぎて、今やいろんな店で食べられる時代になった。目出度し。
一応、海南鶏飯について説明をしておく。
そもそもは中国の海南島の出身者がシンガポールに渡って独自に作り上げたものらしい。海南島にはこの料理は存在しないそうだ(行ったことないんで、伝聞ですんません)。海南人が故郷の料理を東南アジアの各国に広めたと書いてあるものばかりだが、それは間違いみたい。チキンライスに似たものとして、タイの「カオマンガイ」、ベトナムの「コム・ガー」があるが、それらもそれぞれの国で海南人が作ったものなのかもね。
メインとなるのは茹で蒸し鶏もしくはロースト鶏で、鶏スープと生姜で炊き上げたライスの皿で鶏をほぐし、ジンジャー、チリ、ダークソイの3種のソースを自分好みに混ぜ合わせて食べるものだ。「そんなモンに差があるのかよ」ってツッコミ入れられそう。
いや、これが、鶏の質と部位、ソースの味、ライスの味が変わるとけっこう違うんす。いちばん差異が出るのは、鶏の肉質とダークソイの甘さ加減だ。
屋台(ホーカー)からミシュラン店まで食すことができ、国賓にも供される。有名な屋台では長蛇の列を成す、まさにシンガポールを代表する国民食なのである。日本で食べるときに有難いのは、衛生面である。かの国の屋台などでは、いろいろと目をつぶってメシだけを食うこともあるが、日本ではそういうことがないのはいい。
海南鶏飯食堂 麻布十番店
麻布十番と六本木ヒルズの狭間にあって、樹木が生い茂り、ここだけがトロピカルな雰囲気を醸し出している。店内は席間がぎゅっと詰め詰めな感じで、テラス席はペットの同伴が可能だ。白人男性がゴールデン・レトリヴァーをはべらせて、チキンライスを食べていた。なかなか活気があって、店員たちも溌剌としている。BGMはモダンジャズなのだが、いずれも現役バリバリの奏者たちの演奏だ。ガンガンに鳴り響いておるね。
11:45に入店したが、満席だ。12:00になるともう外には列ができている。ほとんどの客はチキンライスを頼んでいるが、雲吞チキンヌードルとか、ココナッツチキンカレーもちらほら。サイドで野菜炒めや海老のブラックペッパーソースなんかを頼んでいるテーブルもある。
さて、最初は例によってチキンスープだ。淡く塩気も少ないが、いい味だ。
チキンライスの登場である。
ライスの炊き方が絶妙な「海南鶏飯食堂 麻布十番店」の”海南鶏飯”。
あたしゃ、チキンを大盛りにした。見た目はなかなか美しい、というか今回の5軒中ではいちばん美しい。肝腎の茹で蒸しチキンは、上半分は脂身がのっていて、下半分は胸肉でさっぱりしている。筆者は脂身があるほうが好みだが、いずれも旨い。隣席の女性は、「きゃ~、やわらか~い。こんなの家じゃできな~い」と嬌声を上げていた。
ソースは3種が付いてくるが、ダークソイソースは薄くはないが濃すぎない、チリソースも柔らかい味だ。ゆえに、ジンジャーソースと3種を混ぜてもとてもバランスがいい。ライスはインディカ米でパラパラ、チキンと生姜の味がする。炊き方が絶妙でとても旨い。サイドで頼んだ中国野菜タオチオ炒めも、シンガポール料理屋であるから甘いけれども甘すぎず、なかなか良い。
日本人の口にかなり寄せているように思った。エビチリやカレーも、けっこうアレンジして日本人に寄せているかもね。味だけを言えば、次の次に紹介する店がいちばん旨いが、サービスなど加味した総合力ではここをトップとして推したい。ちなみに渋谷、恵比寿、横浜にも支店がある。
「海南鶏飯食堂 麻布十番店」の入口
海南鶏飯食堂 麻布十番店
東京都港区六本木6-11-16
中銀マンション裏手
℡03-5474-3200
(月~木)11:30~14:30、17:30~22:00
(金)11:30~14:30、17:30~23:00
(土)11:30~15:00、17:30~23:00
(日)11:30~15:00、17:30~22:00
(祝)11:30~15:00
(祝日前)17:30~23:00
無休
海南鶏飯(普通)(大)(特)1050円、1350円、1750円(税込み)
中国野菜タオチオ炒め 1199円(税込み)
シンガポール海南鶏飯 水道橋店
水道橋の駅から歩いて2分もかからない。白いマーライオンが迎えてくれるからすぐにわかる。15年間、大使館御用達を務めているんだそうだ。今回の5軒の中で、各テーブルに爪楊枝とナプキンと飲み物が置いてあったのは、この店だけだ。しかも、紙エプロンまで用意してある。それだけで、「へー、シンガポールっぽくないねえ、やるじゃないの」となる。日本に較べるとシンガポールは、店によってはコ汚いしサービスも悪い。だから、気持ちはシンガポールのままで、こういう標準的な日本のサービスに出会うと、意表を突かれるね。そして、BGMはずっとサザンだし(笑)。
この店も、いろいろと選ぶことができる。蒸し鶏か、ローストか、あるいは両方のハーフ&ハーフ。+200円で肉の量を1.5倍に出来るし、トッピングパクチーも+200円だ。メニューにはハーフ&ハーフが人気No.1と記してあるね。ワシもそれがええわ。この店は、お盆の上にすべてを載せて一気に出てくる。ライスは茶碗メシだ。珍しい。トッピングパクチーの量もケチくさくない。
「シンガポール海南鶏飯 水道橋店」一番人気の”ハーフ&ハーフ”(蒸し・揚げ)。
さて、まずは蒸し鶏をそのままで食べた。脂がのっていてプルプルと旨い。次にローストだが、これも周囲はこんがり、中は適度に熱が入っていて普通に旨い。お次はソースの味だが、ダークソイソースはトロンと濃い目だが、甘すぎずしょっぱすぎず。チリソースも辛さ控え目。ゆえに、ジンジャーと3種を混ぜても、丁度いい塩梅である。要するに、旨い。
ライスもパラパラのインディカ米で、鶏とジンジャーの味がちゃんとあって、とてもいい。スープも薄味で、キャベツとニンジンが入っているが、普通に旨い。どれもプラス点だから、総合してかなり良いね。大体、今回の5軒は、シンガポール本国と比べてもあまり遜色がない。特に、次のも含めた3軒は出色だ。
とはいえ、余計なことを言うと、私がシンガポールでいちばん好きな店は「文東記」なのである。プルプルでジューシーすぎるチキンライスには圧倒される。噛む度にため息が出るぞ、マジで。一人で食べて、「うめー、うめー」言っていたら、隣の席の中国から来た姉ちゃんに笑われた。店もとても清潔で、良く気が利くスタッフも多いからサービスも完璧だ。「文東記」に匹敵する店は日本にはない(断言)。だが、シンガポールの3番手ぐらいのレベルには届いているような気がするんだな。だから、大満足ではある。
シンガポール海南鶏飯 水道橋店
東京都千代田区神田三崎町2-1-1
美幸ビル2F
℡050-5571-4641
(火・水・木・日・祝)11:00~15:00、17:00~22:00
(金・土)11:00~15:00、17:00~23:00
定休日:月曜
シンガポールチキンライス(蒸し・揚げ・ハーフ&ハーフ) 1000円
お肉の増量(1.5倍) 200円
トッピングパクチー 200円
新東記 CLARK QUAY 大手町
大手町フィナンシャルシティにある店である。シンガポール料理だろ、そんなに客単価は高くないよな。
こんな一等地に店出して大丈夫なのかねえと余計なシンパイをしながら、扉を開けた。ランチタイムをはずして13:30、客は一人しかいなかった。メニューを見ると、海南鶏飯は当然のごとくセットであって、鶏肉の大盛が300円高いだけである。もちろん、大盛りにして(笑)、パクチー200円、旨いと評判の自家製ライムジュースも頼んだ。
はい、来ましたぜ。
サラッと軽めのダークソイソースがかかった「新東記 CLARK QUAY 大手町」の海南鶏飯。
ウォー、鶏肉がドドーンじゃねえか。
ちょっと凄い量だ。気前いいねえ。でも、パクチー200円、こいつが小皿に笑えるぐらいちょっとだけ。こんなん、ひと口で終いや(笑)。パクチーなんかよ、スーパーで一束300円ぐらいちゃうか。あまりにも貧相で、両者の落差にかなり笑えた。
まー、いいや。
しかし、この店のは珍しいぜ。ダークソイソースが初めから鶏肉全部にかけてあるのである。なんでじゃいと思いつつ、一切れを食った。すると、なんということでしょう! この程よい脂身と柔らかさ! 先に触れた「文東記」にいちばん近いかもしれんのお。ソースもダークソイにしてはサラッと軽めで、めちゃくちゃに旨いじゃあないの。へー、たまげた。本国ではドロッとして相当に甘いソースなんだが、この店のはかなり甘さ控え目なところがとてもいいと思う。メニューには、「最高級の銘柄もも肉」と書いてある。ソースがかかったそのままで、二切れ、三切れと夢中になって頬ばった。
鶏スープで炊いたジャスミンライスはタイ米を使っていて、ジンジャーがちょい香ってこれも極上の味やんけ。鶏スープも塩味は控えめだが、非常に旨い。ゆえに総合して、むむむー、予想外の極楽を味わった。
そろそろ、味変タイムだ。自家製のチリソースとジンジャーソースと混ぜ混ぜして、パクチーも混ぜて、ライスとともに食べた。
ん-、やはりこっちがいいね。
欲を言えば、ダークソイソースも含めて、食べ手側にすべてを委ねて欲しいもんだな。まー、それだけこのソースに自信があるのかもしれぬ。たぶん、3種のソースを各テーブルに置くのが面倒だったのかもね(笑)。不思議だったのは、店内の貼り紙。「原材料価格上昇 人手不足 賃上げしました!」ってヤツ。なんかのプロパガンダに見える。階級闘争かよ(笑)。単に「諸物価高騰の折、価格を改定します」とでも書いときゃいいのに。8/16から値段が変わるらしい。
もう一つ不思議だったのは、メニューに「最高級の銘柄もも肉」とあるからさ、会計をしながら、「どこの鶏使っているんですか?」と聞いた。すると、会計の女性が「それには答えられませんッ」とピシャリ。はあ~、なんでや? そんなことが企業秘密なわけ!? 「日本の鶏です」だってさ。「お口に合いましたか?」と聞いてはきたが、モノには言い方ってもんがあるだろう。なんか、モヤモヤしたね。ヘンな店だ。
店員や階級闘争はともかく、海南鶏飯はとにかくトップクラスで旨いことには間違いない。そうだ、自家製ライムジュースも搾りたてで鮮烈。旨かったよ。
「新東記 CLARK QUAY 大手町」の入口
新東記 CLARK QUAY 大手町
東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ102
℡03-6262-5595
(月~木・祝後日)
11:30~15:00、17:00~22:30
(金・祝前日)
11:30~15:00、17:00~23:00
(定休日)土日祝
海南鶏飯 1450円
〃 肉大盛 1750円
自家製ライムジュース 450円
海南チキンライス 夢飯
西荻窪駅北口から歩いて2分ほどのところにある。2000年にオープンというから、もう25年も経つ。南国っぽいラフな雰囲気だ。扉の外から中を伺っていると、「いらっしゃいませ~」と声がかかる。店員はいずれも、いかにも東南アジアが好きそうな服装をしている。BGMはジャクソン5からエラ・フィッツジェラルドが歌った「ヘイ・ジュード」に変わるが、基本的にブラック・ミュージックのようだ。13:30入店でするりと入れたが、引っ切り無しに客がやってくる。人気店だねえ。
この店がいいのは、茹で蒸しチキンとローストチキンのハーフ&ハーフを選べるところ。茹でたのばかりを食っていると、たまにはカオマンガイのような揚げたチキンも食いたくなってくるもんだ。もうひとついいのは、チキンライスに(小)(中)(大)があることである。普通盛りだと腹一杯にはならないことが多いからねえ。
さて、最初に来たのは例によってスープだ。チキンスープだが、具にキャベツと少しだけ豆腐が入っている。キャベツの甘味が染み出して、優しい味だね。時間差で、チキンライスがやって来た。あたしは(中)を頼んだが、一見して、「こりゃ、少ねえな」と思った(笑)。先に茹で蒸しチキンを食べた。脂ものっていて、まずまずだね。次にローストだが、うむ、これはなかなか旨い。どっちかと言うと、ローストに軍配が上がる。で、ライスは生姜が香るが、まー、普通。
3種のソースにレモン汁も付く「海南チキンライス 夢飯」の”ハーフ&ハーフチキンライス”。
ソースは例の3種に加えてレモン汁が付いてくる。ダークソイソースは甘味は薄いがかなり濃厚で、チリソースはけっこう辛い。3種を混ぜても、チリが際立ってくる感じ。なかなか旨いんじゃないすか。でも、パクチーは小指ほどの長さのが1本だけだよ! ケチくせええ。これには驚いたね。パクチー、高いのかなあ?
海南チキンライス 夢飯
杉並区西荻窪北3-21-2 徳田ビル1F
℡03-3394-9191
11:00~20:00
定休日:火曜・水曜
海南チキンライス
(小)880円(中)1030円(大)1280円
ハーフ&ハーフチキンライス
(小)950円(中)1150円(大)1380円
威南記海南鶏飯
2015年7月に田町に出来たシンガポール料理店である。シンガポールの本店は名店なんだって。チャンギ国際空港にも出店があるね。店内は、天井は高く、頭上で大きなファンがゆっくりと旋回していて、いかにもトロピカルな雰囲気だ。屋外テラス席もある。いわゆる大箱だ。人気店なので、ランチのピーク時をはずして13:30頃に行くと、楽に入れた。
混み合ったランチ後だからだろうか、何となく、店員たちの動きがダルい。溌剌さはゼロである。気も利かない。まー、いいや。さて、筆者は食い意地が張ってるから、チキンライスの他にもミニサラダやスープのバクテー、チリプラウンもついてくる「ウィーナムキー ランチセット」を頼んだ。これが、まー、失敗だった。
あたしゃ、チキンライスは死ぬほど好きだが、シンガポール料理はまったく口に合わんのだった(爆)。だから、スープのバクテーもエビチリもアカンのですわ。バクテーのシナモンとかアニスやクローブのスパイス臭、エビチリの辛さよりもあの甘ったるさ、これがダメなのね。ついでに言うと、ココナッツの甘さも苦手だ。同じスパイス使いとしては、タイ料理のほうがはるかに自分には合うね。きわめて大雑把なことを言うと、シンガポール料理はボヤ~ッとしているが、タイ料理はしゃきっと鋭利だ。
結論としては、この店ではチキンライスだけで良かった(笑)。
骨付きが特徴の「威南記海南鶏飯」のチキンライス。
さて、ここのチキンライスで珍しいことが一つ。
蒸し鶏のうち半分は手羽肉で、肉に骨がしっかりと付いていたことだ。シンガポールでは骨付き肉には一度もお目にかかっていないなあ(ちなみに、そういう店も少なからずあるそうだ)。骨付きは、肉から骨をはがさねばならず、食うのがかなり面倒なんである。だが、チキンは、骨が付いている手羽肉のほうが脂身がのっていてプルプルだ。手羽肉にはいきなりガブリとかぶりつけないのだが、残り半分の胸肉よりはずっと旨い。胸肉はぶ厚く淡白ではあるが、柔らかく十分に美味ではあった。
最初は、何もつけずに食べていたが、鶏の肉片とライスにジンジャー、チリ、ダークソイを混ぜたら、さらに旨くなった。鶏スープで炊き上げたライスも、まあ、普通のレベルで特に問題はない。ライスは結構、パラパラな部類だろう。鶏スープ、こいつも普通のレベルでしかなくて、快哉を叫びたくなるようなものではない。
ゆえに、5軒の中では、順番は最後かねえ。すまんね。
「威南記海南鶏飯」の入口
威南記海南鶏飯
東京都港区芝浦3-4-1
田町グランパークプラザ
℡050-3164-9120
(月~金)11:00~14:30、17:30~22:00
(土日・祝)17:00~21:30
ウィーナムキー ランチセット 2400円
スチームチキンライス 1450円
ローストチキンライス 1450円
「これを食べなきゃ人生ソンだよ」とは
うまいものがあると聞けば西へ東へ駆けつけ食べまくる、令和のブリア・サバランか、はたまた古川ロッパの再来かと一部で噂される食べ歩き歴40年超の食い道楽な編集者・バッシーの抱腹絶倒のグルメエッセイ。
筆者プロフィール
食べ歩き歴40年超の食い道楽者・バッシー。日本国内はもちろんのこと、香港には自腹で定期的に中華を食べに行き、旨いもんのために、台湾、シンガポール、バンコク、ソウルにも出かける。某旅行誌編集長時代には、世界中、特にヨーロッパのミシュラン★付き店や、後のWorld Best50店を数多く訪ねる。「天香楼」(香港)の「蟹みそ餡かけ麺」を、食を愛するあらゆる人に食べさせたい。というか、この店の中華料理が世界一好き。別の洋物ベスト1を挙げれば、World Best50で1位になったことがあるスペイン・ジローナの「エル・セジェール・デ・カン・ロカ」。あ~、もう一度行ってみたいモンじゃのお。
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
Lounge
Premium Salon
これを食べなきゃ人生ソンだよ
皮脂や肌のごわつきなどが気になる季節。そのままにしておくと、せっかくお手入れしていても効果が半減してしまいます。そんな時は角質ケアがおすすめ! そこで今回は、洗顔や化粧水など、いつものお手入れでケアできるアイテムをご紹介します。
Events
【開催中〜9/25(木) 東京都・GYRE GALLERY】
2025.7.24
永劫回帰に横たわる虚無三島由紀夫生誕100年=昭和100年
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
2025年、三島由紀夫生誕100年=昭和100年という節目に、東京・表参道のGYRE GALLERYにて、「永劫回帰に横たわる虚無三島由紀夫生誕100年=昭和100年」が9月25日まで開催されている。
アニッシュ・カプーア Untitled 2017年 Gouache on paper h.96.5 × w.115.5 × d.3.5cm [AK0360]
フランスの哲学者ロラン・バルトが、日本を「表徴の帝国」と表現したのはよく知られている。天皇、都市、女形、すき焼き、礼儀作法、パチンコ……中心なき記号の連鎖によって成り立つこの国のありようを、彼は“意味からの自由”と見た。そしてそれは、三島が晩年に遺した「日本はなくなって、その代わりに、無機的な、からっぽな、ニュートラルな、中間色の、富裕な、抜目がない、或る経済的大国が極東の一角に残る」という予見的な言葉とも、不思議な共振を見せる。
杉本 博司 Bay of Sagami, Enoura 2025 gelatin silver print 119.4 x 185.4 cm Negative 615 相模湾、江之浦 2025 ゼラチン・シルバー・プリント 119.4 x 185.4 cm ネガ番号 615
本展では、こうしたバルトと三島の双方が捉えた日本の「空虚」を前提に、杉本博司、森万里子、アニッシュ・カプーア、中西夏之、ジェフ・ウォール、池田謙、平野啓一郎、友沢こたお、という錚々たる現代アーティストたちが、それぞれの表現を通じて、三島由紀夫のデビュー作『仮面の告白』と、遺作『豊饒の海』に込められた壮大なテーマ――「阿頼耶識=相関主義」の一端を浮かび上がらせるもの。
池田 謙 「矛盾の美学ーーAesthetic of Paradox」2025年 サウンドコラージュ
小説『豊饒の海』最終章「天人五衰」(第4巻)における、すべてが瓦解する瞬間。 「この庭には何もない」と語る聡子の台詞は、三島由紀夫が最後に辿り着いた空虚そのものを象徴しており、その空虚の風景に、戦後日本美術の“意味から解放された風景”を重ね合わせていく構成は、アートと文学、哲学の越境的対話となっている。
平野啓一郎 「三島由紀夫論」2025年 書籍、ミックスメディア 40x50x31cm
日本の表徴と三島由紀夫が残したもの、そして受け継がれたこととは何か。本展は、その問いの前で立ち止まり、静かに思索する時間をもたらしてくれるはずだ。
◆永劫回帰に横たわる虚無三島由紀夫生誕100年=昭和100年
【会期】開催中~2025年9月25日(木)
※8月18日(月)休館
【会場】GYRE GALLERY(東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F)
関連リンク
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
関連記事
投稿 永劫回帰に横たわる虚無三島由紀夫生誕100年=昭和100年 は Premium Japan に最初に表示されました。